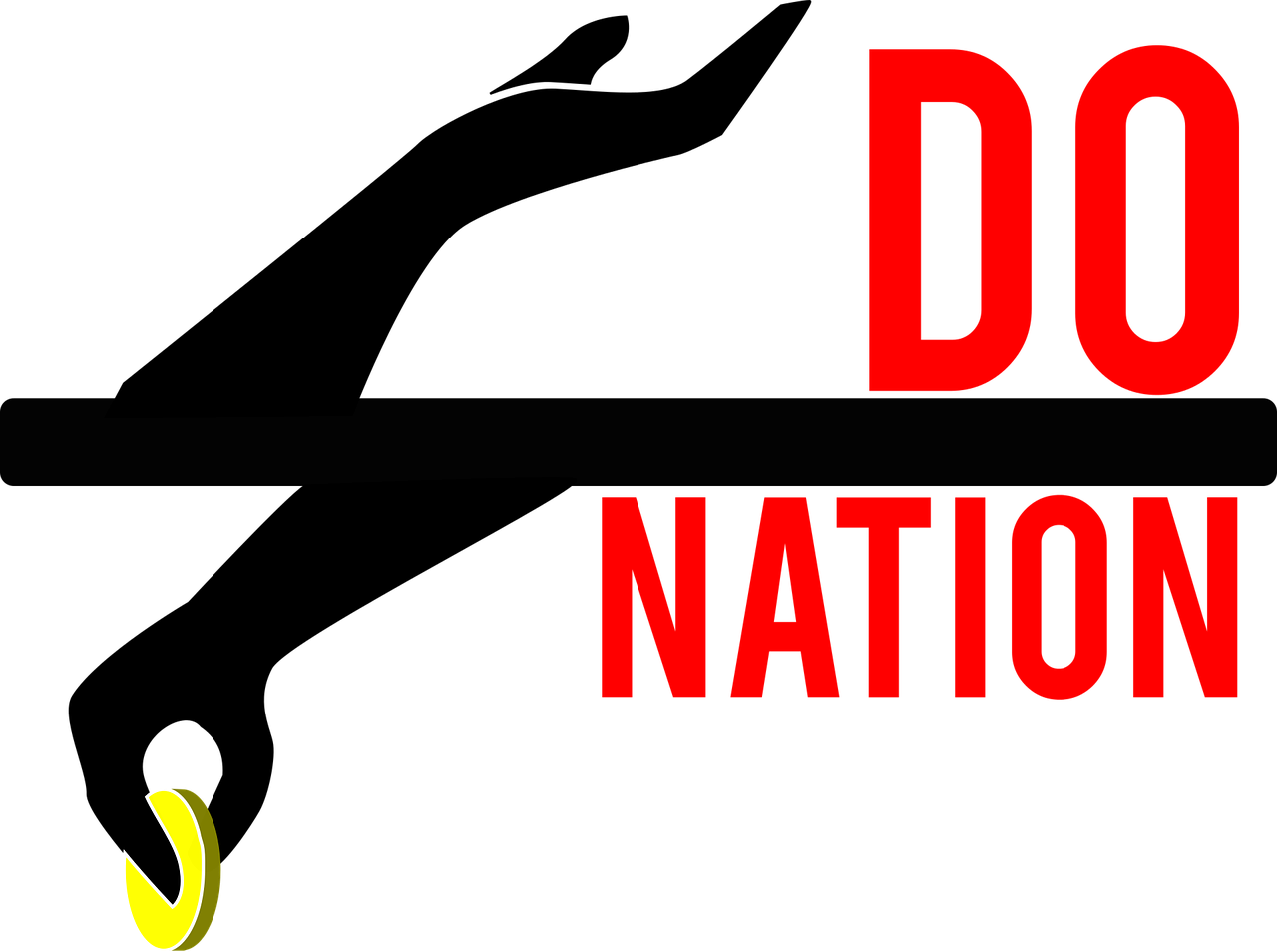
1.義援金と支援金ってどう違う?
西暦2000年前後になると日本各地で被害が出るような大地震が多発したり、地球温暖化などが原因の気候変動による自然災害が多発して、ニュースなどでよく義援金とか支援金という言葉を耳にしますが、どちらも寄付には違いないですがどのような違いがあるのか知らない人も多いと思うので説明します。
【義援金】
義援金はテレビの国営放送局や民放などでよく呼び掛けてお金を集めている募金で、寄付すると赤い羽根が貰える寄附団体や災害の被害を受けた自治体が行っている事が多いです。
後日寄附団体や被害自治体で集めた寄付金をそういった団体が集計してから、被災者の生活支援を目的として配布されます。
ちゃんと均等に分配するために被災者の被害状況などを正確に把握してから配られるため、配られるために時間が掛かると非難を受ける事がありますが、集まったお金はそのまま全額被災者に渡るのが義援金です。
義援金を集めている団体で最も有名なのは日本赤十字社で、集めたお金を分配するだけでなく現地に医療スタッフなどのボランティアを派遣して救護活動や医療活動なども行ってます。
日本赤十字社への寄付金はテレビやラジオなどの放送局やインターネットに加えて、郵便振替や銀行振込や駅前募金など様々な方法で集められています。
次に良く知られている団体に赤い羽根共同募金があり、テレビやラジオなどの放送局や全国展開しているメガバンクへの振り込みや駅前の募金箱などでお金を集めて、そのお金を被災者に対して分配してます。
またこの団体は寄付金の分配だけでなく、後で説明する支援金活動も行っています。
他にも日本ユニセフ協会や有名ポータルサイトが主催している団体や、人気SNSサービスが行っているものや、最近流行りのクラウドファンディングを利用した団体など様々な組織がお金を集めて被災者に分配してます。
【支援金】
それに対して支援金はNPOやNGOなどの団体が寄付金でお金を集めて、被災者に分配するのではなく被災地に生活に必要な食料品や日用品などの物資を購入して届けたり、温かい食べ物を提供するために炊き出しを行ったり、ボランティアを募集して瓦礫の撤去やゴミの片付けなどを手伝ったり、医療ボランティアを集めて医療活動や健康支援をするなどの活動に使われる募金です。
支援金の場合はNPOやNGOの活動内容を調べれば寄付金の使われ方が分かるので、自分がして欲しい活動をやっている団体を選んで寄付する事が可能です。
私は被災者に直接お金を分配する義援金よりは、使われ方が明確に解るこちらの支援金の方が寄付した実感がわくので、主に募金は支援金の方でするようにしています。
また支援金を集めたNPOやNGOなどの団体は、集めたお金を分配するわけではなく、使用用途が既に決まっているために、初動が素早くて支援を行うスペシャリストが活動しているという点も気に入って寄付してます。
支援金はTVやラジオの放送局や募金箱などでの募金はほとんど行ってなくて、その団体の公式ホームページに書かれている入金方法やクラウドファンディングなどでお金を集めています。
NPOやNGO団体には様々な団体があって、レスキュー隊の派遣を行ったり医療や救助ヘリの派遣や、現地の病院や医師や看護婦や救助犬などの派遣を行っている医療レスキュー系の団体があります。
それ以外にも世界中の数十か国の医師がボランティアスタッフとして所属している多国籍医師ボランティア派遣を行っているNGO団体も存在します。
海外のNGOですが日本国内にも多数の外国人ボランティア医師が派遣されて、日本の地震などの災害の時に医療活動を行ってました。
他にも日本国内で被災地を調査して必要になっている物資を調査して、本当に必要になっている物資を購入して届けるNPO団体や、集めた支援金を使ってその被災地で活動する小さなNPO団体に資金援助をしているNPO団体など様々な団体があります。
2.ふるさと納税について
義援金や支援金を使った寄附以外でも災害被災地の復興に貢献できる寄付金制度にふるさと納税があります。
ふるさと納税というと豪華な返礼品を目当てに行うので後ろめたいと考える人もいますが、被災地に行う場合には返礼品を希望しないとい使い方も可能です。
返礼品なしで純粋な寄付金として集まったお金は、その全額が被災した自治体に届けられて、被災者に直接災害支援金として配られたり、被災して壊れた住宅を再建するために助成金などの財源に用いられます。
またふるさと納税にて被災地から返礼品で農作物や酪農製品を貰うのがなんだか後ろめたいと考える人もいますが、農作物や酪農製品を自治体が買い上げて返礼品で送るので、地元の農業や畜産業の復興の協力する事になり地元産業の復興に貢献してます。
そういう理由から私は地震や津波による被害を受けた自治体の豪華な返礼品のあるふるさと納税を積極的に行ってます。
それ以外にも最近ではSNSが発達した事に因って、個人的に被災地でお金に困っている被災者本人が寄付を呼び掛けている事もあるので、SNS経由での寄付をする事も可能です。






